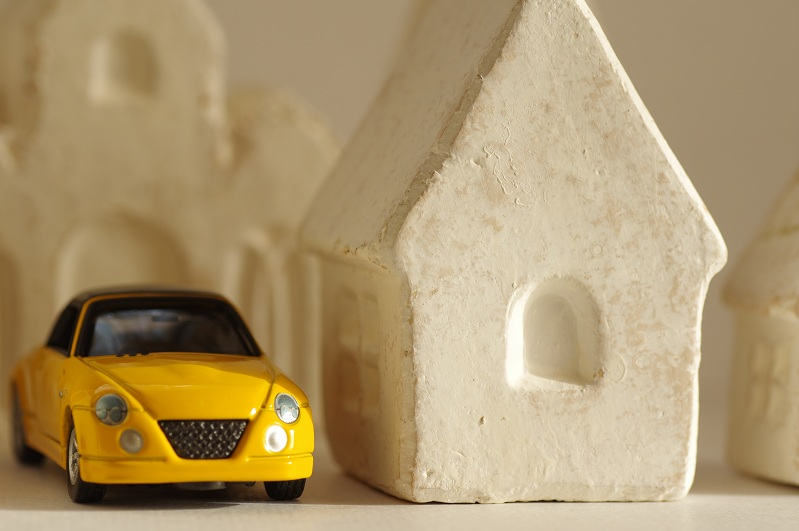社員の自家用車は業務に使用できる?メリットや注意点も解説!
感染症対策をきっかけに、自家用車(マイカー)での通勤や業務利用を認める企業が増えています。その一方で、事故やトラブルへの対策に不安を感じている企業も少なくないのではないでしょうか。
この記事でわかること
- マイカーを業務で使用する際の注意点
- 車両管理規程を作成する際のポイント
- マイカーに対するアルコールチェックの対応方法
正しい運用を行うことで、交通事故やトラブルを防ぎ、自家用車を安全に活用しましょう。
執筆者:Bqey(ビーキー)編集部
Bqey編集部は、企業の車両管理に精通したチームです。運営元は、国内外の自動車メーカーに部品を供給するサプライヤーである株式会社東海理化の新事業部門。製造現場で培った技術と知見を活かし、効率的な車両管理を支援するシステムを開発・提供しています。記事では、安全運転や車両運用に役立つ情報をわかりやすく発信しています。
自家用車でもアルコールチェックは必要?!
義務化対応、チェックリストで簡単に確認!
実は、自家用車であっても業務で使う場合は、アルコールチェックが義務化されています。
うっかり対応漏れがあると、法令違反になる可能性も。
自社の運用は大丈夫?今すぐ確認できるチェックリストを無料でご用意しました!
【チェックリストの一例】
- アルコールチェックはいつ行う?
- 検知器はどんな性能が必要?
- 他の事業所で運転する社員はどう管理する?
- 管理者が不在・遠隔の場合の確認は?
アルコールチェック義務化を正しく理解し、安心・安全な運用を。
ぜひ、自社の状況と照らし合わせてチェックしてみてください!
アルコールチェック義務化に対応するには、「運用を支える仕組み」づくりが欠かせません。
Bqey(ビーキー)は、飲酒検知時のエンジンロックや顔認証による本人確認など、飲酒運転を未然に防ぐための機能を搭載した車両管理システムです。
アルコールチェックの記録をクラウドで一元管理し、管理者の負担も軽減します。
そもそも、自家用車とは?
「自家用車」という言葉は身近なものですが、その指し示す範囲は状況によって少し異なります。法律上の広い意味合いと、私たちが普段使う一般的なイメージ、そして社用車との違いについて、以下で解説します。
法律上の「自家用自動車」は全ての「白ナンバー車」
「自家用車」について明確に定義した法律はないようですが、「自家用自動車」については道路運送法で「事業用自動車ではないすべての自動車」と定義されています。
- 業務用自動車(緑ナンバー):「有償」で荷物や人を目的地に運ぶトラック・バス・タクシーなどの事業用自動車
- 自家用自動車(白ナンバー):「無償」で自社の荷物や人を運ぶ、事業用自動車以外の車両
この法律上の分類に従うと、個人が所有するマイカーだけでなく、企業が業務に使う「社用車(営業車など)」も、白ナンバーであれば法律上は「自家用自動車」に含まれます。
一般的なイメージは「自家用車=マイカー」
ただし、私たちが日常会話で「自家用車」と言うときは、多くの場合「個人が所有し、通勤や買い物、レジャーといった私的な目的で使う車」、つまり「マイカー」を指しています。
本記事では、そのようなマイカーを業務で使用する場合のメリットや注意点について解説していきます。
マイカーと社用車の主な違い
本題に入る前に、まずは「マイカー」と「社用車」の違いを整理しておきましょう。両者の位置づけを理解しておくことで、後に紹介するメリットや注意点もより明確になります。
| 比較項目 | 自家用車(マイカー) | 社用車 |
|---|---|---|
|
所有者 |
個人 |
法人(会社) |
| 使用する人 | 所有者本人とその家族など |
会社の従業員 |
|
主な使用目的 |
通勤、買い物、レジャーなど私的な利用 |
営業、荷物の運搬など会社の業務 |
|
費用負担 |
車両購入費、税金、保険料、維持費など全て個人が負担 |
会社が経費として負担 |
マイカーを業務使用するメリットと注意点
近年、働き方改革の影響でリモートワークや在宅勤務を認める企業が増え、それに伴い、自宅から取引先へ直行できるようマイカーの業務使用を許可する企業も増えています。
社用車の利用のために出社する必要がなくなり、通勤時間の短縮や車両保有台数の削減につながるなど、企業・従業員の双方に多くのメリットがあります。一方で、注意すべき点も少なくありません。
企業のメリットと注意点
メリット
- 社用車の購入費用や保険料・駐車場代が削減できる
- 公共交通機関での通勤時の感染症リスクを減らすことができる
注意点
- プライベートと業務利用の線引きが難しくトラブル対応が複雑になる
- 車両工事を伴うシステム(動態管理など)難しい
マイカー利用の最大のメリットは、自動車購入にかかる費用や保険料の削減など車両コストを大きく経費削減できる面です。
ただし、通勤中や業務中に私用車で事故が発生した場合はもちろん企業も責任が問われることになります。導入する際はしっかりと規程を設け、トラブル時でも適切に対応できるように運用する必要があります。
社員のメリットと注意点
メリット
- 荷物が多くても楽に移動できる
- 社用車を利用するためだけに出勤する必要がない
- 公共交通機関で出勤するよりも移動時間が削減でき業務効率が上がる
注意点
- ガソリン代などの経費申請作業が増える
- 天候によって、混雑状況が大きく左右されることがある
- 駐車場やメンテナンス費用などの負担が増える
企業が対応すべき8つのポイント
マイカーの業務使用は便利な反面、事故が起きたときの責任の所在や補償範囲が曖昧になりやすいというリスクがあります。「本人の車だから自己責任」と思われがちですが、実際には業務命令下での使用であれば、会社にも使用者責任が及ぶ可能性があります。
こうしたトラブルを防ぐには、マイカーの業務使用を社内規程として明文化し、使用条件・保険加入・安全管理などを明確にしておくことが不可欠です。以下では、規程整備の際に企業が押さえるべき8つのポイントを解説します。
①使用の許可基準と使用範囲を明確にする
まず、誰がどのような条件で、どこまでマイカーを使用できるのか、という大前提を定義します。
許可基準の具体化
- 客観的な基準:自宅から会社までの距離(例:〇km以上)、最寄り公共交通機関までの距離など
- 運転者に関する基準:運転経験(例:免許取得後〇年以上)、過去の事故・違反歴
- 車両に関する基準:対人・対物無制限の任意保険加入(必須)、定期的な点検整備の実施、過度な改造がされていないこと
使用範囲の限定
- 通勤利用:自宅と会社の往復のみに限定するのか
- 業務利用: 営業や出張など、会社の業務での使用を許可するのか
※許可しない場合は、規程に「業務使用の禁止」を明記することが重要 - 同乗者の規定:業務利用時の同乗者を従業員に限定するなど、同乗者に関するルールも定めておくと安心
②費用負担の範囲と精算方法を定める
費用に関する取り決めは、従業員とのトラブルを避けるために最も重要な項目の一つです。
ガソリン代・交通費
- 実費精算、または「1kmあたり〇円」といった距離に応じた精算が一般的
- 通勤手当と業務利用時の交通費の切り分けの明確化
駐車場代
- 会社指定の駐車場を用意するのか、従業員が用意するのか
※従業員が用意した駐車場を会社が負担する場合、上限金額を設定する - 業務で訪問先のコインパーキング等を利用した場合の精算ルール
車両維持に関する手当
業務利用は車両の消耗を早めるため、オイル交換代やタイヤ代などの維持費を考慮した「車両手当」を支給することが望ましいです。支給の有無、金額、条件を明記します。
③任意保険の加入を義務付け、条件を明記する
自賠責保険だけでは、事故の賠償金を到底カバーできません。会社の最大のリスクヘッジとして、任意保険の加入を許可の絶対条件とします。
- 加入の義務化: 必ず任意保険に加入していることを利用の条件とする
- 補償内容の指定: 「対人・対物賠償 無制限」を必須条件とすることを推奨
- 保険区分の確認:「日常・レジャー」「通勤・通学」「業務使用」の区分のうち、使用実態(例:月15日以上業務で利用)に合った区分に変更する必要があるかを確認
※保険料が上がる場合は、その差額の負担者を会社・従業員のどちらにするか事前に協議し、定めておく
④安全運転の義務と遵守事項を課す
従業員の安全意識を高め、事故を未然に防ぐための具体的なルールを記載します。
- 道路交通法の遵守を大前提とする
- 運転中のスマートフォン・携帯電話の操作および通話の禁止
- 「ながら運転」や漫然運転の禁止と、休憩に関する指導
- 定期的な安全運転講習の実施や情報提供
死亡事故の原因で上位となっている「漫然運転」については、以下の記事も参考にしてください。
⑤事故発生時の対応フローを定める
事故の当事者はパニックに陥りがちです。落ち着いて行動できるよう、報告・連絡・相談のフローを時系列で分かりやすく規定します。
- 負傷者の救護と危険防止措置
- 警察への通報(110番)と指示を仰ぐ
- 相手方の情報確認
- 会社への報告(直属の上司、管理部門など報告ルートを明記)
- 保険会社への連絡
緊急連絡先や報告すべき内容(日時、場所、状況など)をフォーマット化しておくと、よりスムーズです。
⑥会社への提出書類を義務付ける
許可条件を満たしているかの確認や、万が一の際に備えるため、以下の書類のコピー提出を義務付けます。
- 運転免許証
- 車検証
- 自賠責保険証明書
- 任意保険証券
これらの書類には有効期限があるため、「年に一度」など定期的に提出させ、管理することが重要です。
⑦許可の有効期間と取り消し条件を設ける
会社や従業員の状況や環境は変化する可能性があるため、許可の有効期間と、問題があった際に許可を取り消せる条件を明記します。
有効期限
許可の有効期限を「1年間」などと定め、更新制とする運用がおすすめです。
取り消し条件
- 免許停止・取り消し処分を受けた場合
- 任意保険を解約した場合
- 重大な交通違反や交通事故を起こした場合
- 会社の規程に違反した場合
⑧会社の免責範囲を明確にする
会社の責任範囲を明記し、無用なトラブルを防ぎます。
- 従業員が無断で私的利用していた際の事故
- 飲酒運転、無免許運転など、従業員の重大な法令違反に起因する事故
- スピード違反などの交通違反による反則金・罰金は、運転者本人の責任であること
社内規程の整備方法は大きくわけて「車両管理規程」にマイカー使用に関するルールを追記するスタイルと、マイカー専用の規程を作成するスタイルがあります。一般的には前者のスタイルが多く見られますが、社用車と業務使用するマイカーの比率や利用頻度、管理体制に応じて柔軟に判断するとよいでしょう。
これから車両管理規程を作成したい、現在の規程の見直しをしたい方は、以下の記事をぜひ参考にしてください。カスタマイズして今すぐ使えるWord形式のテンプレートも、無料でダウンロードできます。
事故が起きたときの責任は?
マイカーを業務使用している最中に事故が発生した場合、基本的には運転者本人が第一義的に責任を負うことになります。もちろん、交通違反や過失の有無に応じて損害賠償の範囲も変わります。
しかし注意したいのは、事故が会社の業務命令に基づく使用だった場合です。この場合、会社にも使用者責任(民法715条)が及ぶ可能性があります。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索第七百十五条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
例えば、営業命令でマイカーを使用して訪問先へ行く途中に事故を起こした場合、会社側も一定の責任を問われることがあります。事故が起きた場合の責任範囲や補償範囲は、規程作成と合わせて整理し、明確にしておきましょう。
安全確保のために企業が取るべき対策
事故やトラブルを未然に防ぐには、企業としての安全確保の仕組みも欠かせません。具体的には以下のような取り組みが考えられます。
①アルコールチェックや運転日報の提出
運転前後のアルコールチェックは、社員自身の安全意識を高めるだけでなく、万が一事故が発生した場合の重要な証拠としても役立ちます。
また、日報による運転状況の記録は、運転時間や走行距離の把握に加え、運転傾向の分析にもつながります。例えば、長時間運転や頻繁な深夜運転が続いている場合、管理者が早めに注意喚起を行うことも可能です。
安全運転管理者の選任対象となっている企業では、アルコールチェックや運転日報の記録・管理は法令上の義務となっています。マイカーを業務使用する場合も確実に対応しましょう。
安全運転管理者の選任条件
安全運転管理者を選任しなければならないのは、以下の条件に当てはまる企業や事業所です。
- 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している
- 5台以上の自家用自動車を使用している
(原動機付自転車を除く自動二輪は1台につき自動車0.5台として計算)
なお、自動車を20台以上使用している事業所では、安全運転管理者に加えて「副安全運転管理者」の選任も必要です。安全運転管理者や副安全運転管理者については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
参考記事:5分でわかる「安全運転管理者」とは?選任義務の条件や資格、罰則も解説
参考記事:副安全運転管理者は必要?安全運転管理者との違いや業務内容も解説
アルコールチェックの実施内容
アルコールチェックのタイミングや確認方法、記録の保存期間などについては、以下のように法令で定められています。
- 対象者: 業務で自動車を運転する全ての従業員(マイカーを業務で運転する場合も含む)
- タイミング: 運転前と運転後の計2回
- 確認方法:運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などを目視等で確認した上で、アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認する
- 記録と保存: チェック結果を記録簿に記録し、その記録を1年間保存する
直行直帰などで対面での確認が難しい場合でも、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させ、電話やビデオ通話などで結果を報告させるなど、確実に実施できる運用体制を構築する必要があります。
アルコールチェックの実施方法や記録項目などについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
②安全運転者教育や定期点検の徹底
社内の安全運転教育や法定・日常点検の実施を規程化することで、事故リスクを大幅に減らせます。特にマイカーを業務で使用する場合、車両状態の把握が個人任せになりがちです
そこで、安全運転教育を継続的に実施し、点検や整備の記録を確認する仕組みを作ることが重要です。これにより、社員一人ひとりの意識向上だけでなく、社内全体の安全文化の醸成にもつながります。
安全運転教育について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
参考記事:安全運転教育とは?社内教育の具体例や事故防止に役立つツールも紹介
③車両管理システムの活用
車両管理システムとは、運転日報、点検記録、アルコールチェック結果などをクラウドで一元管理できるツールのことです。管理者の負担を減らしながら運用の抜け漏れを防ぐことができます。
システムによっては、運転中に危険な挙動があった場合にリアルタイムで警告・通知する機能や、ドラレコと連携して運転傾向を評価する機能、アルコールチェック結果によって車両の利用を制限する機能などがあり、安全運転管理を強力にサポートしてくれます。
車両管理システムについては、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
参考記事:【2025年最新】車両管理システムおすすめ12選|機能を徹底比較!まとめ
自家用車(マイカー)の業務使用は、適切に運用すればコスト削減や働き方の柔軟化など、多くのメリットをもたらします。
一方で、ルール整備や安全管理を怠ると、思わぬ事故や責任問題に発展しかねません。企業としては、業務使用に関する規程を整備し、補償や責任の範囲を明文化しておくことが重要です。
さらに、「アルコールチェック・運転日報」「安全運転教育」「車両管理システムの活用」といった仕組みを組み合わせることで、安全運転管理を確実に実施できます。リスクを最小限に抑えながら、柔軟で効率的な車両運用を実現していきましょう。
最近注目されている車両管理システム
『Bqey(ビーキー)』をご存じですか?
Bqeyは「使い勝手満足度92.3%」とお客様の満足度が非常に高い車両管理システムです。
社用車管理システムBqeyなら、
- 煩雑になりがちな社用車の予約が簡単にできる
- アルコールチェック記録など、義務化で増えた業務を簡略化
- 日報類を全てデジタルで完結し、ペーパーレス化を促進
など、車の管理者とドライバー双方の負担を軽減し、業務効率を改善できる機能が充実!
社用車の課題をまるっと解決するBqeyについて知りたい方は、ぜひこちらの資料をご覧ください。