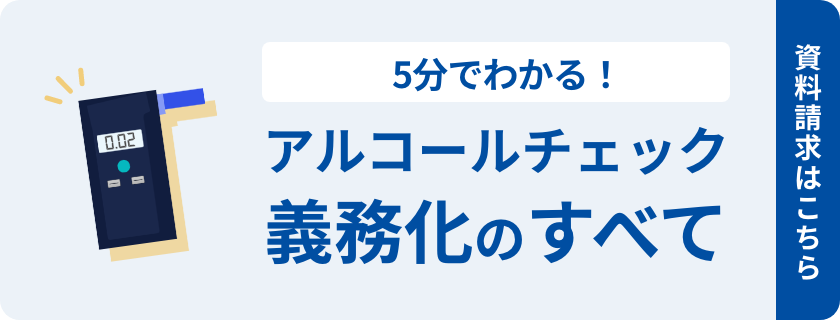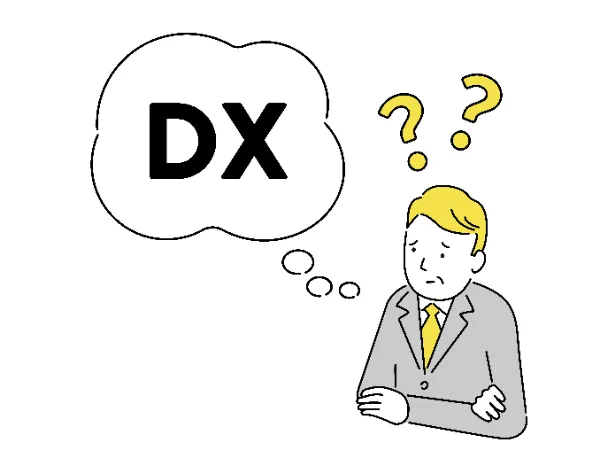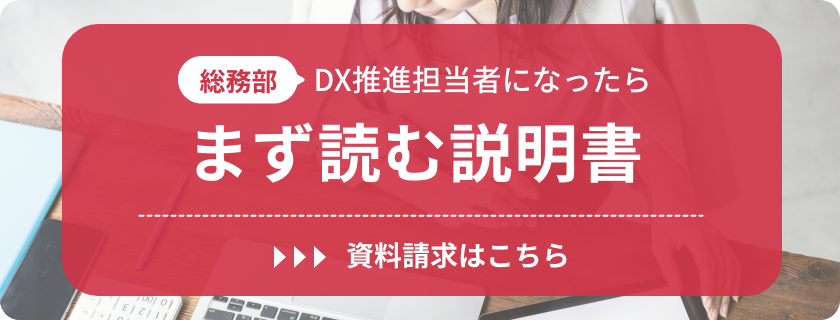バックオフィスのDX戦略とは?2023年をバックオフィスのDX化元年にしよう
企業業務を滞りなく進めるために、重要な役割を担うバックオフィス。長引くコロナ禍やテレワーク推進の流れにより、バックオフィスのDX化に注目が集まっています。
この記事では、バックオフィスのDXを推し進めるポイントや注意点などをまとめました。「バックオフィス業務を少しでも効率化して、従業員の負担を減らしたい」「生産性を高めたい」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
バックオフィスのDX化とは
そもそも、バックオフィスのDX化とは、どのようなことを意味するのでしょうか。基本的な知識を押さえておきましょう。
そもそも、バックオフィスの業務とは?
バックオフィスとは、フロントオフィスと対比してよく使われる言葉です。辞書によると、バックオフィスは「企業の中で事務処理的な業務を行う部門」とされます。顧客との接点をもつ部門であるフロントオフィスに対し、バックオフィスは顧客と直接接する機会はありません。部門としては、総務や人事・生産管理部門などが含まれます。
ちなみに、バックオフィスには「後方支援」という意味もあります。その意味では、バックオフィスの中のバックオフィスと言えるのが、総務部門です。「他部署に属さないけれど会社業務を円滑に進めるための業務」を請け負う、潤滑油の役割を担っています。
引用:コトバンク フロントオフィス/バックオフィスとは
「バックオフィスをDX化する」とは?
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、「デジタルによる変革」の意です。そもそも、バックオフィスは紙の書類を扱う作業が多いため、デジタル機器・ソフトの導入でDX化しやすいのです。
最近ではインターネットやITツールが普及し、専門知識がなくとも、デジタルツールを簡単に使いやすくなりました。バックオフィスの担う業務をデジタル化することで、業務を大幅に改善する可能性が期待されています。
バックオフィスのDXが重要である理由
ここからは、なぜ今バックオフィスのDXが重要視されているのか、主な理由を2つ解説します。
業務効率化・コスト削減の必要がある
バックオフィスの業務は、顧客との接点がない分、利益に直結しないと考えられる傾向があります。そのため、業務を効率化し、コストを削減することが要求されやすいのです。
政府主導で進められている働き方改革では、イノベーションによって生産性を高めることが推奨されています。また、2020年から始まったコロナ禍はまだまだ終息が見えず、業務を非対面でも行えるようにすることが、リスクヘッジのためにも必要です。
総務や経理・人事などのバックオフィスをDX化し、システムやツールに任せられる業務は移行して、より生産性を高めることが求められています。
人手が不足している
前述のように、バックオフィスはコスト削減が要請されやすいため、人員が補充されにくい傾向があります。少人数で業務を回していると、いわゆる属人化が進み「その人がいないとわからない」といった状況が起こりがちです。
また、担当者が病気になったり、出社できなかったりすると、たちまち業務が回らなくなるリスクもあります。
バックオフィスのDX化で得られる効果
ここからは、バックオフィスをDX化することにより、どのようなプラスの効果が得られるのか、詳しく見ていきましょう。
生産性を向上し、コスト削減につながる
総務を始めとしたバックオフィス業務には、それまでの経験を基にして決まった手順で行うものが多くあります。前述のように、紙ベースで行われている業務も多いです。そのような業務をDX化することで、業務を効率化し、従業員のリソースを確保することが期待できます。
最近では、バックオフィス向けのITツール・サービスも充実しています。紙の代わりにそれらのツールを使い、アクセスしやすいクラウドデータなどで管理することが、DX化の第一歩となります。
属人化を防止し、ヒューマンエラーを削減できる
バックオフィス業務をDX化すれば、さまざまなデータややるべきタスクを可視化できるようになります。そうすれば、業務の属人化を防止し、業務が滞るリスクを軽減できます。
そもそも人間による判断や予測・経験則などを必要としない作業であれば、システムを使ったほうが処理は早く、正確です。
DX化によりヒューマンエラーを減らして、企業利益を守る効果が期待できます。
データを一元管理し、経営判断に活かせる
紙ベースでは探すのも一苦労だった各種データですが、ツールを使えばリアルタイムに保存したり、一元管理したりできるため、経営者が経営判断を行いやすくなります。
例えば社用車専門の管理ツールを使えば、予約状況や稼働状況を可視化して戦略策定に活かせます。クラウド管理を行えるサービスを使えば、遠隔地にいてもオフィスにいるときと同様にデータにアクセスできるため、効率的です。
バックオフィスのDX戦略のポイント・注意点
ここからは、バックオフィスをDX化するときにどのような点に注意したらよいか、3つのポイントから解説します。
DXの目的を明確にする
バックオフィスをDX化したいと考えるのは、どのような問題意識からでしょうか。DX化の目的を定めると、手段やツールの選定基準を作ることができます。
DX化には、一例として以下のような目的が置かれることが多いです。
- 業務効率化で、従業員の満足度を上げる
- テレワークや非対面でコロナ禍対策をする
- コスト削減を行う
自社の場合にはどのような目的があるか、整理してDX化に取り組むと効率的でしょう。
組織のルール・体制に照らして使いやすいものを選ぶ
組織のルールや体制に照らしてツールを選べば、ツールを使う工程になじみやすく、標準化しやすくなります。
例えば社用車の管理をDX化する場合、自社サービスのサーバーと連携したいか、社用車管理システム側のサーバーを使って手軽に利用したいかなど、組織によってニーズが異なります。
ツールなどの新たな導入にあたっては、経営層も巻き込んだうえで、担当者の意見を取り入れて選定することが大切です。
既存のコストと削減可能なコストを総合的に考える
DX化のためにツールを導入すると、導入コストや月額利用料がかかるケースもあります。しかし、DX化によって削減できるコストもあるため、総合的に考えることが大切です。
例えば社用車の稼働状況をデータから把握したり、デジタルキーの付与でシェアリングしやすくして社用車の台数を減らし、コスト削減に成功した事例もあります。
また、従業員のモチベーションアップや離職率の削減など、長い目で見て企業の利益や成長につながることもあります。目先の損得にとらわれず、ぜひ長期的な影響も含めて検討してみましょう。
まとめ
バックオフィスのDX化には、生産性向上や属人化防止などのさまざまなメリットがあります。オンラインでもデータ確認や手続きができるようにすれば、対面で業務を行う必要がなくなり、働き方改革にもつながります。
DXによるペーパーレス化・業務効率化は、法整備が行われるなど国でも積極的に推進されています。社内リソースを有効に活用するためにも、まずはバックオフィスから業務変化に取り組んでみませんか?
弊社の提供する「Bqey」は、社用車管理を手軽・一元的に行えるサービスです。社用車の予約や運転日報の作成・鍵の付与などをオンラインで行うことにより、バックオフィスを煩わせていた業務を効率化できます。
社用車管理に課題をお感じの方は、ぜひ下記のサービスページをご覧ください。BqeyによるDX事例もご紹介しておりますので、お気軽に資料をご請求ください。
資料請求はこちらから!